
代表取締役社長 桑原 功
地域とともに歩み続ける
地域とともに歩み続ける
山陽新聞の前身である山陽新報は、1879(明治12)年1月4日に創刊されました。以来、「地域とともに」という基本姿勢を貫き、地域や読者の皆さまと喜怒哀楽をともにしながら、明治、大正、昭和、平成、そして令和と、147年にわたって紙齢を重ねてまいりました。
創刊号の社説には、「あまねく山陽の事情を写出し、世間有益のことを論述し、もって大いに教化殖産の道を裨益(ひえき)せんとす」と発行の目的が記されています。日々の出来事を正確、公正、客観的に伝え、解説や論評によって人々に最適な判断材料を提供し、こうした言論報道活動を通してよりよい地域づくりに貢献する。この創刊の精神は、いまもいささかも変わっておりません。
デジタル化の進展を踏まえ、伝統的な紙の新聞とともに会員制電子版「山陽新聞デジタル」(愛称・さんデジ)に力を入れており、紙とデジタルの双方の特性を生かし、より速く、より分かりやすく正確なニュース発信に努めています。さんデジは2024年12月にリニューアルし、地域の話題、国内外の出来事が探しやすく、読みやすくなりました。グループには新聞を核に、テレビ、ケーブルテレビ、FMラジオ、生活情報紙といったメディアがあり、さまざまなチャンネルを通して情報をお届けしています。
民主主義の基盤を支えるジャーナリズム機能を発揮しながら、持続可能な地域づくりに地元紙として役立ちたい―。その思いから2021年にスタートした「吉備の環プロジェクト」では、山陽新聞グループ社員がチームを編成し、岡山県内をほぼくまなく回り、住民の声、思いを聞き取って得た情報をもとに、地域と連携して課題解決や魅力向上につながる活動に取り組んでいます。
時代は大きな転換期を迎えています。紛争と対立で揺らぐ国際秩序、激甚化する自然災害、国内では急速な少子高齢化がさまざまな分野に影響を及ぼし、地域課題を顕在化させています。デジタル化の進展は社会、産業構造を大きく変える一方、負の側面として、ネットに誤情報や偽情報があふれ、社会の対立や分断を助長する事態を招いています。
先行きの不透明な時代にあって、山陽新聞社は、ジャーナリズム機能に一層磨きをかけながら、地域の人と人をつなぎ、一体感を醸成し、ともに課題解決の道筋を探ることで、地域社会の羅針盤としての役割を果たしてまいります。これからも地域とともに歩み続けます。


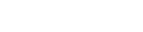
 山陽新聞社
山陽新聞社