
2025トップインタビュー
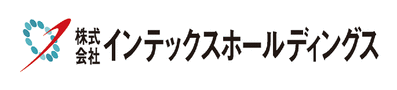

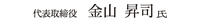
問われるのは人間力
—葬祭業の業界動向は?人口減とはいえ、高齢者に偏った人口構成ですから、「多死社会」という言葉まで生まれており、葬祭業にとって、ベーシックな需要は拡大傾向にあるのは事実。それを視野に入れて、異業種からの参入が顕著になっています。もちろん、この業界は免許制ではなく、表面的には参入のハードルが低いわけです。加えて葬儀会社を選ぶ際、従前の地縁・人縁よりも、ネットでのコンタクトポイントが不可欠な時代。「ネット葬儀社」と称される業者も現れている状況です。
一方、葬儀自体の簡素化の流れは歯止めがかかりません。不況下における節約志向にコロナ禍が拍車をかけたわけです。従って、1件あたりの平均単価が下がり、取扱件数は横ばいや微増していっても、売上高は減少しつつあるというのが現況になります。
—そのような状況下で、どのように対処されるのでしょうか。
私たちの信念は、「葬儀葬祭は人間の尊厳に最も近い仕事」というもの。故人はもちろん、お見送りに集うすべての方々の想(おも)いにお応えできるご葬儀を具現化させていただく。さらに、遺されたご遺族の方々へのケアまでも含め、形だけのホスピタリティーではなく、「心」対「心」、「人間」対「人間」のおもてなしを実践していくことこそが、私たちの矜持(きょうじ)です。
ですから、単にコストのみで語る葬儀には異を唱えます。人数の多寡に関わらず、すべてのご葬儀に想いを込めることに全集中しています。
そこで問われるのが、社員一人一人の人間力。人間力を備えた人材がいる企業は、不測の事態にも柔軟に対応できるのです。そうした人材を育てることが、経営者の務めと考えています。
—倉敷商工会議所会頭としての取り組みなどについてお聞かせください。
倉敷は、日本でも有数の観光資源を有する都市。これをさらに生かしていくため、広域商工会議所連携の枠組みの中で、姫路商工会議所との広域観光ルートの設定が実現しました。大阪・関西万博の年でもあり、インバウンドも含めた観光需要の受け皿整備を進めたいと考えます。
また、昨年の能登半島地震で浮き彫りになった課題の一つが、地元建設土木業界の人手不足。これについては、市内の高校の土木科新設に向け、岡山県教育委員会へ要望書を提出しました。


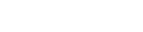

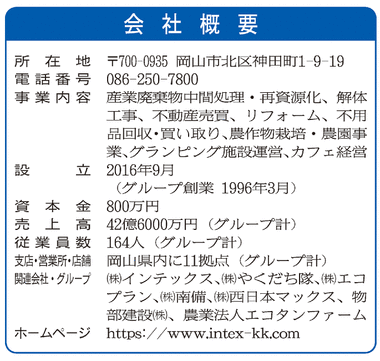
 山陽新聞社
山陽新聞社